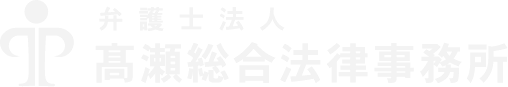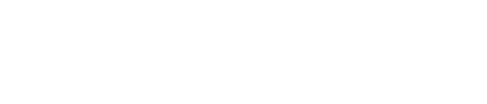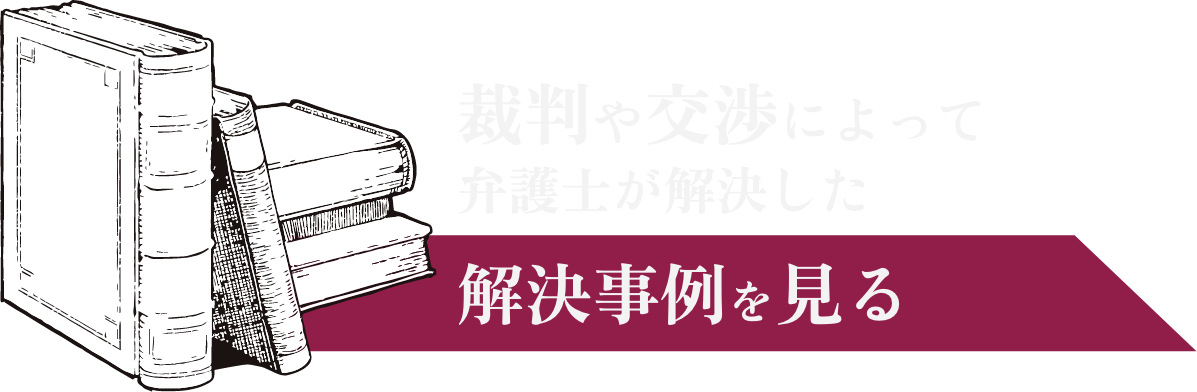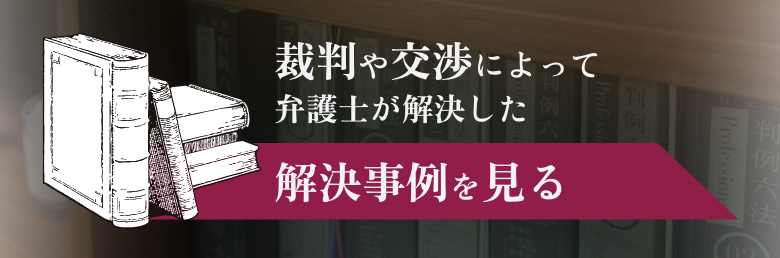2025.10.23
人事労務トラブルになりうる「グレーゾーン」

人事労務の現場では、明確に違法と判断できるケースよりも、判断が分かれるグレーゾーンの方が圧倒的に多く存在します。法律上は一見セーフに見えても、実際の裁判例や行政の運用を踏まえるとアウトに近い場合もあり、経営者・人事担当者を悩ませる要因となっています。こうした「グレーゾーン」は放置するとトラブルが表面化し、訴訟や労基署対応に発展することも少なくありません。
よくあるグレーゾーンの具体例
1. 長時間労働と残業代
- タイムカードと実労働時間に乖離がある
- 管理職扱いにして残業代を支払っていないが、実態は権限が不十分
企業が「黙認」していると未払い残業代請求に直結します。
2. ハラスメントの線引き
- 部下への強い指導が「教育」か「パワハラ」か
- 仲間内の冗談が「セクハラ」認定されるかどうか
ハラスメントの境界線は極めてあいまいで、相談窓口の対応を誤れば企業責任が問われる可能性があります。
3. 有期雇用契約・雇止め
- 「次回も更新するつもり」と言っていたのに突然の雇止め
- 更新回数が多く、実質的に無期契約に近い扱い
裁判では労働者に有利な判断が出やすく、安易な契約終了はリスクを高めます。
4. メンタル不調社員の扱い
- 業務軽減を求められたが、どこまで対応すべきか
- 長期休職中の従業員を復職させるか解雇するか
「安全配慮義務」「解雇権濫用法理」との兼ね合いがあり、慎重な対応が必要です。
5. 副業・SNS利用
- 社員がSNSに会社批判を書き込んだ
- 副業先での行動が会社の信用を害するかどうか
懲戒処分の妥当性はケースごとに異なり、グレーゾーンが多い領域です。
これらの事案に共通して言えるのは、「グレーゾーンだからこそ後で大問題になりやすい」ということです。
- ハラスメントを放置 → 労働者が外部機関(労基署・労働局)に相談
- SNSや社内で不満が拡大 → 企業イメージの失墜
- 裁判になれば長期化・コスト増大
こうしたリスクは、初期段階で弁護士が介入すれば、事前にトラブルを回避したり、適法かつ合理的な社内対応を整理したりすることで最小化できます。
人事労務のトラブルは顧問弁護士がおすすめ

人事労務のトラブルは、明確な違法行為よりも「判断に迷うグレーゾーン」から生じるケースが圧倒的に多いのが実情です。経営者や人事担当者が「これって大丈夫かな?」と感じた時点で、早めに弁護士へ相談することが、最も効果的なリスクヘッジになります。
私たち髙瀬総合法律事務所には、企業事情に精通した弁護士が在籍し、契約書作成や顧問弁護士契約においては百数十件を超える豊富な実績があります。特に顧問契約を結んでいただくことで、就業規則や雇用契約の整備から、人事労務トラブルの対応まで一括してお任せいただけるため、多くの企業様から高い満足をいただいています。