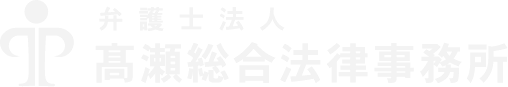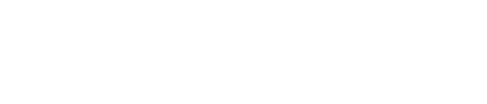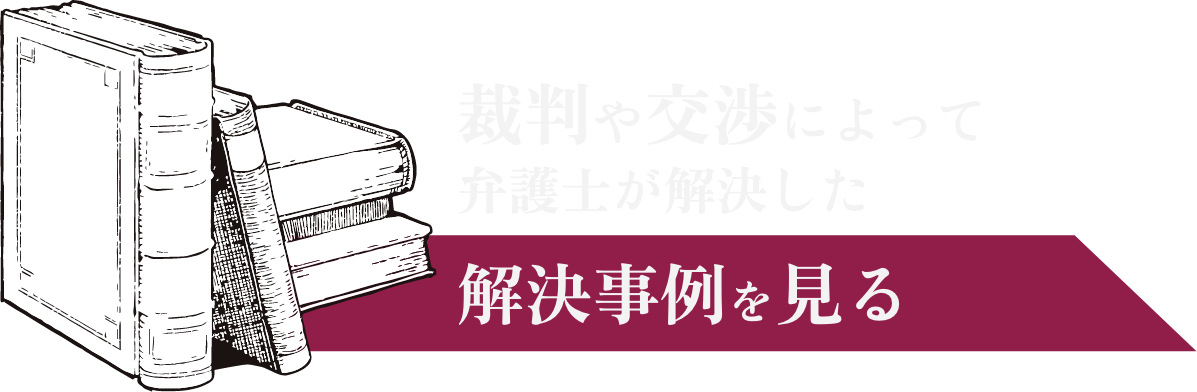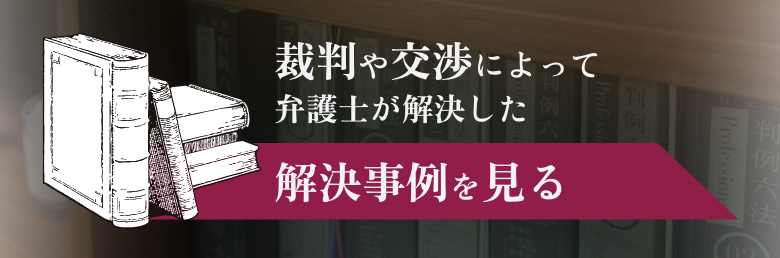2025.05.13
途中解約はできる?契約の“解除権”と“損害賠償”の基本

― 双方の立場での対応策、違約金条項の有効性も考察 ―
契約書を取り交わす場面は、日々の企業活動において避けて通れません。取引開始時には順調に見えた契約でも、やむを得ない事情で「途中解約」が必要となることがあります。しかし一方で、契約を一方的に解除すれば「損害賠償」や「違約金」の問題に発展することも。
本コラムでは、契約の解除権の基本、途中解約の際の注意点、そして契約書作成段階での予防策について、企業法務に詳しい弁護士の視点から解説します。
途中解約と解除権の違いとは?

「途中解約」と「解除」は、実務上は似た意味で使われがちですが、法的には明確に区別されます。
- 解除権とは、契約成立後に特定の事情が生じた場合に契約を終了させる権利です。たとえば「債務不履行」や「合意による解除」が代表的です。
- 途中解約は、定期的・継続的契約(例:業務委託契約や賃貸借契約など)を、契約期間の途中で一方が終了させることを指します。解除と異なり、「将来に向けた契約の終了」が基本です。
契約の性質によっては、民法上当然に解約が認められるケースもあれば、契約書に解除事由を定めておく必要がある場合もあります。
弁護士解説!契約の「途中解約」と「解除権」の違い
| 概念 | 意味 | 典型例 |
|---|---|---|
| 解除権 | 契約成立後、特定の事情があったときに契約を終わらせる権利 | 債務不履行・合意解除 |
| 途中解約 | 定期的な契約を契約期間中に終了すること | 業務委託契約の中途終了など |
💡 定期契約では、一方的な途中解約が制限されていることも。契約書の条項がカギになります!
損害賠償や違約金は請求される?

契約途中で解除する場合、相手方に生じた損害について賠償責任が生じる可能性があります。
特に注目すべきは、契約書に記載された「違約金」条項の存在です。
- 違約金とは、契約違反があった際に支払うべき金額をあらかじめ定めるものです。これは“損害額の予定”として民法上も認められており、裁判においても原則として有効とされます(ただし、著しく過大な金額は無効となることも)。
- 実際に解除が正当な理由に基づくものであっても、「契約書に違約金条項がある」場合は、支払義務が発生する可能性があります。
したがって、契約を解除する側・される側ともに、契約書の条項をしっかりと確認することが必要不可欠です。
双方の立場からみた途中解約時の対応策

解約を検討している側
- 契約書の解除条項を確認する:解除権が限定されていないかを必ずチェックしましょう。
- 相手との交渉も視野に:事前通知や代替案を提示することで、円満な解決につながる可能性もあります。
- 弁護士に相談する:損害賠償や違約金のリスクを把握した上での戦略的判断が求められます。
解約される側
- 契約不履行の有無を検討:相手の解除が無効である可能性がないか、事実関係を整理します。
- 証拠を確保する:やりとりのメールや契約履行状況を記録し、トラブルに備えましょう。
- 弁護士と連携し対応する:損害賠償の主張や違約金請求の実効性を見極め、交渉を優位に進めるための助言を得ましょう。
契約書作成段階での予防が最も重要

企業法務の現場では、契約トラブルの多くが「契約書に明確な定めがない」ことに起因します。
以下のポイントを押さえた契約書作成を心がけましょう。
- 解除事由や違約金を具体的に記載する
- 通知期間(例:30日前通知)を明記する
- 損害賠償範囲の限定条項を設けることで、予見可能性を高める
- 片務的に不利な条項がないか、弁護士のチェックを受ける
弁護士に相談するメリットとは

途中解約は、単なる意思表示では済まされず、法的リスクや実務上の損害に発展する恐れがあります。
契約書の内容や業種特有の事情によって対応が異なるため、経験豊富な弁護士に早めに相談することが最も効果的なリスク回避策です。
企業の信頼性を守り、取引先とのトラブルを未然に防ぐためにも、契約書の見直しや解除時の対応について弁護士の助言を活用しましょう。
企業法務に強い弁護士がサポートします

契約書の作成・途中解約・違約金の問題は、早めの対策がカギです。
トラブルを未然に防ぎ、企業の信頼を守りましょう。
契約書の作成や途中解約に関するお悩みは、企業法務に強い弁護士へお気軽にご相談ください。
- 契約書レビュー・作成
- 解約トラブルの事前相談・代理交渉
- 損害賠償・違約金対応の法的アドバイス
「弁護士に相談するほどではないと思っていた…」
そんな方こそ、一度お気軽にご相談ください。