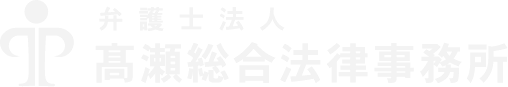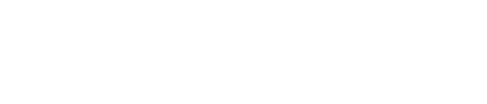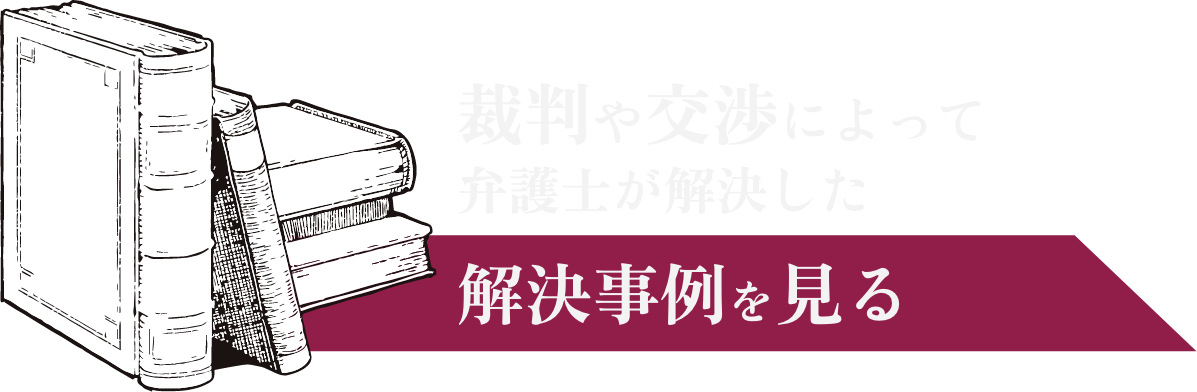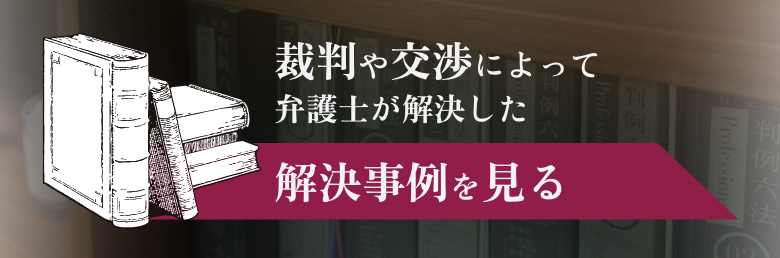2025.04.10
契約書はどちらが作成する?企業法務の現場で求められる戦略的な判断

契約書作成の主導権を巡る実務の現実
契約交渉の場面で「契約書はどちらが作るのか?」という話になることがありますが、これが意外と重要なポイントです。特にBtoB取引やM&A、技術提携のように契約内容が複雑になってくると、契約書をどちらが主導して作成するかで、交渉の進め方やリスク管理のしやすさが大きく変わってきます。
原則:契約書は“提案する側”が作成する
実務では、契約書は「提案する側」が作成することが多いのが現実です。というのも、自社にとって有利な条件をベースに交渉を始められるからです。
たとえば、下記のようなケースが典型です。
- 売買契約 売主が契約書を提示するのが一般的
- 業務委託契約 委託者(発注者)が契約書を用意することが多い
- 投資契約 出資者側がドラフトを作成するケースが主流
こうした原則は「慣例」と「交渉力のバランス」によって成り立っており、実際の現場では必ずしも一律ではありません。場合によっては、受け手側が交渉の主導権を握って契約書を提示するケースも十分にあり得ます。
契約書をどちらが作るかで変わる“主導権”
契約書を自社で作成できると、交渉を自分たちのペースで進めやすくなります。たとえば、
- 自社にとって不利な条文が入りにくくなる
- 想定されるリスクを踏まえた条項(解除条件や損害賠償の範囲など)を先に盛り込める
- 曖昧な表現を避け、トラブルの芽を減らせる
- 全体の流れを設計しやすくなるため、交渉全体をリードしやすくなる
逆に、相手が作った契約書をベースに話を進める場合はこちらは「チェックする側」。すでに組み立てられたルールの中で、見落としがないか、どこを修正すべきかを冷静に見極める必要があります。特に専門的な条文や曖昧な表現には注意が必要で、法務の視点が欠かせません。
弁護士が勧める「契約書作成の進め方」

契約書は、ただ弁護士に丸投げすれば安心…というわけではありません。ビジネスの実情を理解したうえで、法務と連携して進めることで、より実践的で納得感のある契約書が仕上がります。以下のようなステップを踏むことをおすすめします。
1. ビジネスの内容とリスクを整理する
まずは、契約の目的や取引内容、期間、金額、知的財産の取り扱い、契約解除の条件など、事前に社内で情報を整理します。ここが曖昧だと、契約書にもズレが出やすくなります。
2. ひな形があれば、それを活用して調整
社内で使っている契約書のフォーマットがあれば、それをベースにアレンジするのが効率的です。ひな形がない場合は、弁護士がリスクに配慮しながらゼロからドラフトを作成することになります。
3. 弁護士によるチェックでリスクを回避
契約書がある程度まとまったら、専門の弁護士によるリーガルチェックを。見落としがちなリスクや法的に不安定な表現を修正することで、後々のトラブルを未然に防げます。
4. 交渉フェーズでは「落とし所」の判断がカギ
実際の交渉が始まったら、弁護士と相談しながら「どこは譲っていいか」「ここだけは死守する」など、戦略を整理して臨むのが理想です。法的な視点とビジネス的な現実をすり合わせておくことで、スムーズに着地させることができます。
新宿で企業法務に強い弁護士がサポートします
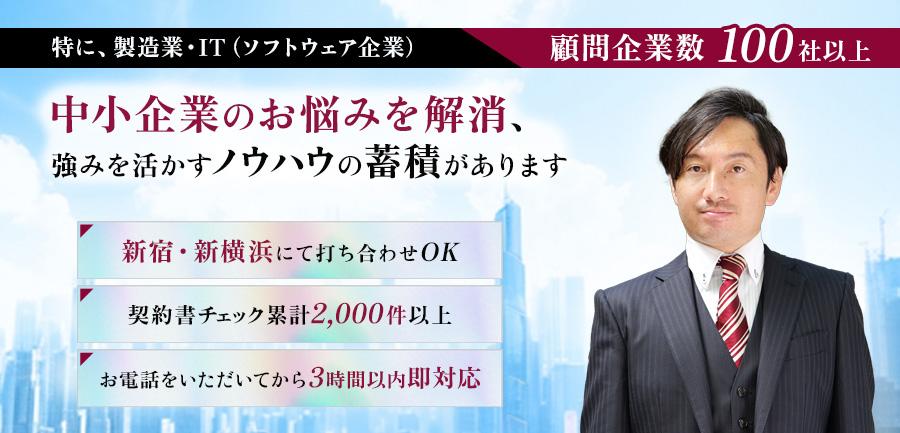
私たち事務所は、企業法務・契約法務を中心に、IPO準備、M&A、知的財産関連契約などの高度な契約実務に数多く携わってきました。契約書を作成する立場であれ、レビューする立場であれ、交渉とリスクの主導権を握ることが貴社のビジネスの安定につながります。
契約書を戦略的に扱いたい企業様は、お気軽にご相談ください。