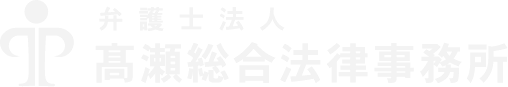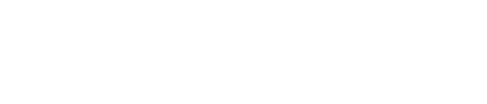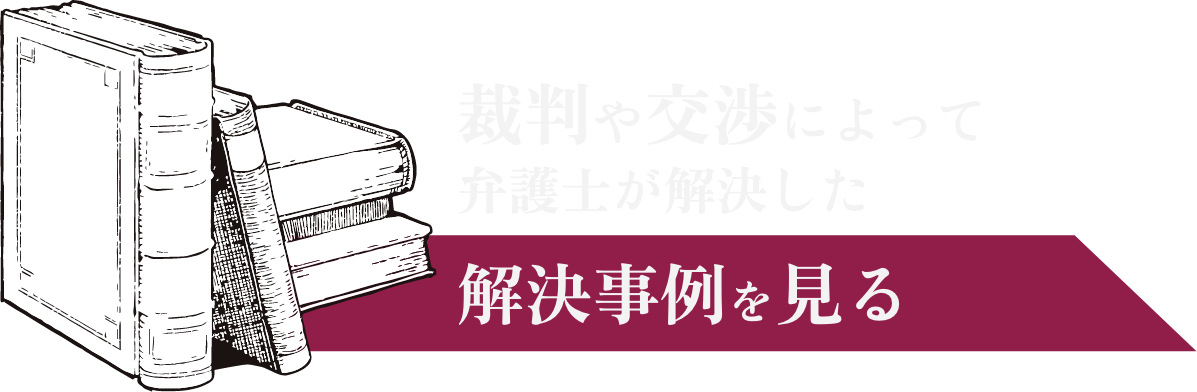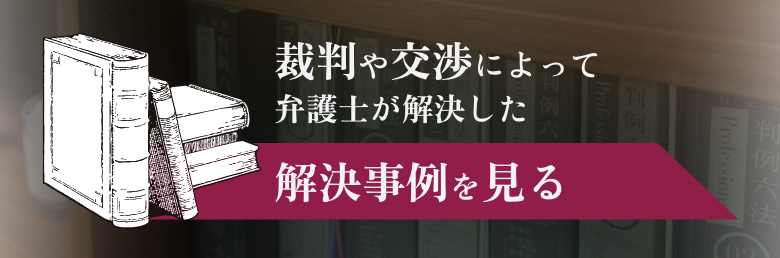2025.03.27
どうする?従業員同士の喧嘩、いざこざが発生した時、経営者が考えたい事

企業を経営する上で、集団で仕事をする以上、人同士のやり取りは避けられません。さらに、従業員の数が増えるにつれ、相性の合わない従業員が出てきたり、摩擦が深刻化することもあります。
こうした小さな従業員同士のトラブルも、時間が経つにつれて悪化し、毎日顔を合わせる環境の中で対立が激化することがあります。その結果、単なる口論や衝突が労務問題へと発展し、最終的には会社の責任が問われるケースも少なくありません。
本記事では、経営者が弁護士に相談すべき状況とその重要性について解説します。
弁護士が相談いただく
従業員同士のトラブルの典型例

職場で発生する従業員同士のトラブルには、以下のようなケースがあります。
- 意見の対立がエスカレートし、暴力行為に発展するような口論や喧嘩
- パワハラやセクハラなど、職場環境に悪影響を及ぼすハラスメント行為
- 業務の進め方や評価を巡る業務上の対立
- 社内恋愛のもつれや金銭問題などの私的なトラブル
このようなトラブルが発生した際、「当人同士の問題だから当人で解決すればよい」と放置したり、適切な対応をしなければ、被害を受けた従業員から会社の責任を追及される可能性があります。
会社の責任はどこまで問われるのか?

労働契約法や労働安全衛生法には、企業には職場環境を適切に整える義務があると定められています。特に、次のような点が問題視される可能性があります。
- 安全配慮義務→会社は従業員が安全に働ける環境を提供する責任を負う。
- 職場環境の整備義務→ハラスメントの防止策を講じる必要がある。
- 使用者責任(民法715条)→従業員の行為が業務の範囲内で行われた場合、会社が責任を負うことも。
使用者責任(民法715条)の具体例
たとえば、営業職の従業員が勤務時間中に顧客訪問のために車を運転していた際、不注意による交通事故を起こした場合、この行為が業務の範囲内であると認められると、会社が被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
また、工場勤務の従業員が作業中に同僚に怪我を負わせた場合も、業務上の指導や命令が関係している場合は、会社の責任が問われることがあります。
これらの義務を怠ると、会社は損害賠償請求や行政指導の対象となるリスクがあります。
経営者が介入すべきボーダーラインチェックリスト

経営者が従業員同士のトラブルに介入するべきかどうかを判断するボーダーラインとして、以下の基準が考えられます。
- 業務に支障が出ているか?
→仕事の進行が妨げられている場合や、チームワークが崩れて業績に悪影響を及ぼす場合は注意。 - トラブルが暴力やハラスメントに発展しているか?
→暴言、身体的な暴力、パワハラ・セクハラが発生している場合は即座に介入が必要。 - 他の従業員に悪影響を与えていないか?
→トラブルが周囲の士気低下や職場環境の悪化を引き起こしていないか聞き取りが必要です。 - 法的責任が発生する可能性があるか?
- →労働基準法違反や民事・刑事問題につながる可能性がある場合。
- 当事者間で解決できる可能性があるか?
- →些細な言い争いや意見の違いであれば、まずは当事者間の話し合いを促す方が良いでしょう。または管理職や人事担当にお互いの言い分をヒヤリングしてもらい、落としどころを探る、配置転換できるものであればしてしまうのも一つの手です。
以上のボーダーラインをチェックした上で、適切な対応をとるべきと考えられます。
その中でも特に法的リスクがある場合は、速やかに弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
法的リスクって?労働基準法違反や民事・刑事問題につながる具体例
- 長時間労働の放置
従業員同士のいざこざや摩擦から従業員が残業を強いられ、それに伴う健康被害が発生した場合、労働基準法違反として会社が責任を問われる可能性がある。 - ハラスメントの未対応
上司や同僚からのハラスメントを会社が放置した場合、被害者が民事訴訟を起こす可能性がある。 - 暴力事件の発生
職場での暴力行為に対し、会社が適切な対応を取らなかった場合、安全配慮義務違反や使用者責任を問われることがある。 - 個人情報の流出
従業員同士のトラブルにより、機密情報や個人情報が漏洩した場合、企業の責任が問われる可能性がある。
弁護士に相談すべきタイミング
従業員同士のトラブルが発生した際、以下の状況では弁護士への相談が不可欠です。
- トラブルがエスカレートし、暴力行為が発生した場合
- ハラスメントやパワハラの訴えがあった場合
- トラブルが原因で従業員が退職・休職を申し出た場合
- 従業員から会社の責任を追及する通知や訴訟の可能性が示唆された場合
- 会社としてどのように対応すべきか判断に迷う場合
弁護士に相談することで、トラブル発生時に迅速かつ適切な対応を取ることで問題の深刻化を防ぎ、会社の責任を最小限に抑え、法的リスクを減らして労務トラブルを未然に防ぐことができます。
また、再発防止策として就業規則の改善を弁護士とともに進めることができ、適切な対応を行うことで職場の秩序を保ち、従業員との信頼関係を維持することにもつながります。
まとめ
弁護士に相談することで、トラブル発生時に迅速かつ適切な対応を取ることができ、問題の深刻化を防ぎ、会社の責任を最小限に抑え、法的リスクを減らして労務トラブルを未然に防ぐことができます。
また、再発防止策として就業規則の改善を弁護士とともに進めることが可能となり、適切な対応を行うことで職場の秩序を保ち、従業員との信頼関係を維持することにもつながります。
従業員同士のトラブルは、会社の責任問題に発展する可能性があるため、適切な対応が求められます。特に、労務問題として訴えられるリスクがある場合は、早めに弁護士に相談し、法的観点からの対応策を検討することが重要です。
「喧嘩やトラブルが発生したが、どこまで会社が対応すべきか分からない…」
というような状況に直面したら、ぜひ弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。
また、労務問題は継続的な対応が求められるため、顧問弁護士を契約することで、日常的な法的アドバイスを受けられ、リスク管理の強化が可能になります。早めに顧問弁護士の導入も検討し、安定した労務管理を実現しましょう。