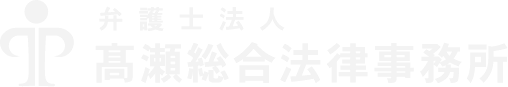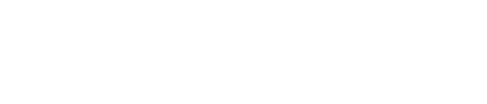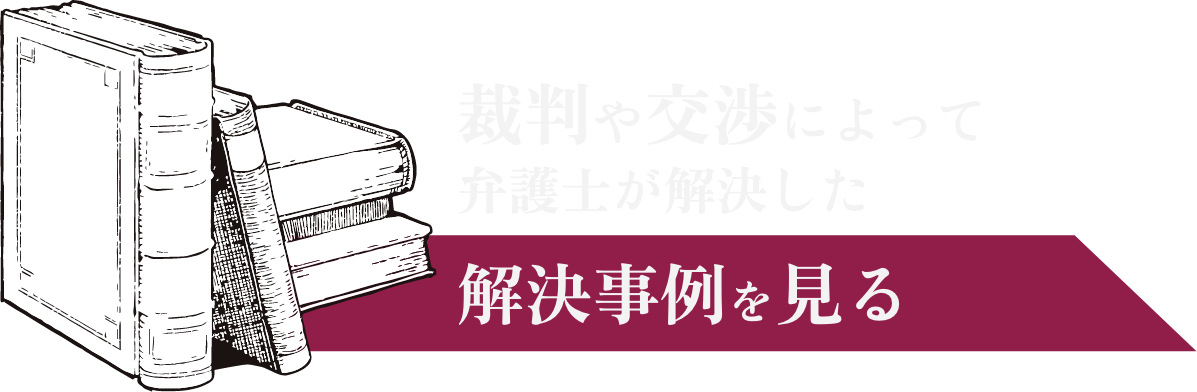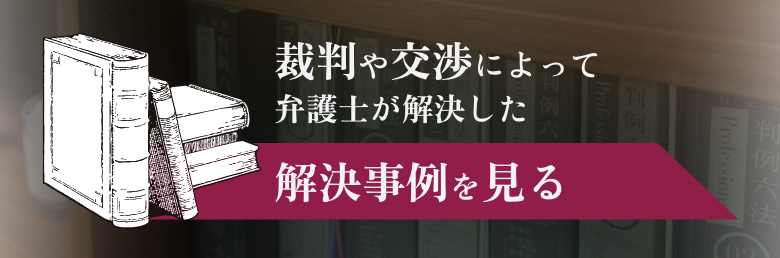2025.05.08
いま企業に求められる「AIポリシー」とは?
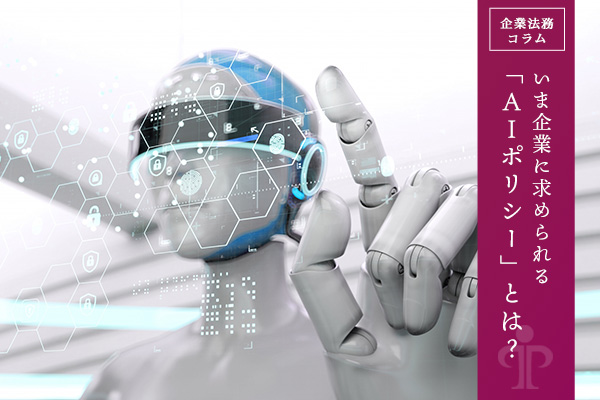
生成AI時代の企業リスクとルール整備のすすめ
AIの活用がビジネスの現場に急速に浸透する昨今、「AIポリシー」の策定は、企業経営において避けて通れない課題となりつつあります。
AIによって業務効率や生産性が大きく向上する一方で、「誰が責任を持つのか?」「著作権や個人情報の取り扱いはどうするのか?」といったリスクも複雑化しています。
このような中で注目されているのが、AIポリシーの策定によるルールの明確化です。
なぜAIポリシーが必要なのか?
- 法令遵守と透明性の確保
AIを業務に取り入れる際、個人情報保護法や著作権法との適合性は避けて通れません。また、社内外に対して「どこまでAIを使い、どこで人が判断しているか」を明らかにする説明責任も問われます。 - 誤情報や差別的出力といったリスク管理
生成AIの出力には誤りや偏りが含まれることも。AIの活用に一定のルールを定めることで、炎上や信用失墜といった企業リスクの軽減につながります。 - 社内利用におけるルールの統一と教育効果
部署や担当者によってAIの使い方に差があると、意図しないトラブルを招きます。AIポリシーを整備することで、全社的に一貫した行動基準が生まれ、従業員教育の土台にもなります。
よく使われる名称とその傾向
AIポリシーには明確な法的名称はありませんが、以下のような名称が広く使われています。
| 名称 | 特徴 |
|---|---|
| AIポリシー | 汎用性が高く、全社的な方針として活用される |
| AI倫理ポリシー | 倫理・社会的責任に重きを置く(主に対外向け) |
| AI利用方針/利用ガイドライン | 社内の業務ルールを中心に定める実務文書 |
| 生成AIポリシー | ChatGPT等の活用に特化したルール設定 |
実際の企業・機関における実例
- 経済産業省:AI利活用ガイドライン
- 富士通:AI倫理ポリシー
- NTTデータ:AI倫理指針
- 電通グループ:生成AIポリシー
このように、大手企業や行政機関でもAI活用に際して明確なスタンスとルールを文書化しています。
そのAIポリシー、本当に大丈夫ですか? 弁護士が“抜け漏れ”を防ぎます
AIポリシーは、単なるガイドラインではなく、企業の“信頼力”を左右するルールブックです。
適切に整備することで、対外的な説明責任を果たせるだけでなく、社内の混乱やリスクの芽を事前に摘むことができます。
弁護士が関与することで、
- 最新の法規制との整合性を担保
- 責任の所在やリスク対応を明文化
- 社内規程・契約書との整合もチェック
といった専門的な交通整理ができるため、「とにかくAIを使えばよい」という誤った認識から抜け出し、“安心して活用できる環境”を構築することが可能になります。
おわりに。AIを活用するなら、まずはルールの整備から

生成AIは便利な道具である一方で、法的責任や信頼性を伴う存在でもあります。
御社の業務内容や体制に合った「オーダーメイドのAIポリシー」を策定するには、法務の専門家である弁護士との連携が最も効率的です。
貴社のAI活用に、法的な安心を。
まずはお気軽にご相談ください。
高瀬総合法律事務所ではAIポリシーの相談など、企業のお悩みを法律のプロが法務目線で相談に応じます。
初回相談60分(60分間の内、10分間のヒヤリング・アンケート時間を頂戴します。)
面談は私たち事務所東京新宿西口のTokyo officeまたは相模原 橋本のKanagawa office、ビジネスに便利な新横浜 Yokohama officeにて対応可能です。
その他、電話やZoomでも柔軟に対応可能です。